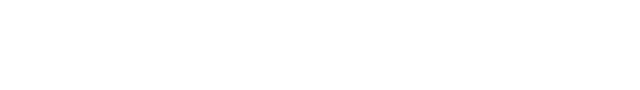健康診断で「血小板が低い」と言われたら
血液検査の結果に「血小板が少ない」と書かれていると、不安になる方も多いと思います。
しかし血小板減少(thrombocytopenia)は、一過性の反応から骨髄疾患まで幅広い原因で生じる現象です。
ここでは、日本血液学会や内科学会のエビデンスをもとに、正確な見方と次にすべき対応を解説します。
血小板とは何か
血小板は骨髄内の巨核球(megakaryocyte)から放出される細胞断片で、血液1μLあたり13〜35万個程度が正常範囲です。
主な役割は血管損傷時の一次止血(血小板血栓の形成)であり、止血に関わる重要な細胞成分です。
寿命は約10日、脾臓に1/3程度がプールされています。
血小板が低下する原因分類
血小板減少は大きく次の4機序で整理されます(日本血液学会分類 2023年版)。
| 病態機序 | 主な疾患・原因 | 機序の概要 |
|---|---|---|
| 1. 産生低下 | 骨髄抑制(再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、白血病、抗がん剤・放射線) | 巨核球の減少・成熟障害 |
| 2. 破壊亢進 | 免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)、薬剤性(ペニシリン系、キニジン、抗てんかん薬など)、膠原病(SLE) | 抗体による免疫学的破壊 |
| 3. 消費亢進 | DIC、TTP/HUS、重症感染症、敗血症 | 血栓形成に伴う消費 |
| 4. 分布異常 | 肝硬変・脾腫による脾プール増加 | 脾臓への隔離 |
このうち**最も頻度が高いのは「偽性」および「免疫性(ITP)」**です。
一過性・偽性低下に注意
健診レベルで最も多いのが**偽性血小板減少(EDTA依存性凝集)です。
採血後の抗凝固剤EDTAにより血小板が凝集し、機械的に低値を示すもの。
再採血でクエン酸Na採血管やヘパリン管を用いると正常化します。
文献的には全血検体の約0.1〜0.2%**に認められると報告されています(Blood. 1984;63:1114)。
また、一時的なウイルス感染(感冒、EBウイルス、インフルエンザなど)後にも一過性の低下を認めることがあります。
免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)
慢性的に血小板が10万/μL未満の場合、**免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)**を疑います。
ITPは自己抗体により血小板が脾臓で破壊される疾患で、発症率は人口10万人あたり3〜4人。
多くは軽症で経過観察可能ですが、3万/μL以下では出血リスクが上昇します。
-
特徴:血小板以外の血球は正常、骨髄で巨核球増加
-
鑑別:薬剤性、SLE、HIV、C型肝炎などの二次性ITPを除外する必要
-
治療指標:血小板3万/μL未満または出血傾向ありで治療開始(ステロイド、トロンボポエチン受容体作動薬など)
(参考:日本血液学会 ITP診療ガイドライン 2023)
薬剤性血小板減少
薬剤による免疫性血小板減少も重要です。
抗菌薬(ペニシリン系、セファロスポリン系、スルホンアミド)、抗てんかん薬、利尿薬(フロセミド)、ヘパリン(HIT)などが知られています。
特にヘパリン起因性血小板減少症(HIT)は動脈・静脈血栓症を伴うため、緊急対応が必要です。
脾腫・肝疾患との関連
慢性肝疾患(肝硬変、C型肝炎など)では、脾腫による血小板プール拡大が原因で低値を示すことがあります。
脾臓が腫大すると血小板が隔離され、実際の血小板産生は正常でも末梢血では低値となります。
DIC・TTPなど重症疾患
感染症や悪性腫瘍でDIC(播種性血管内凝固症候群)が起きると、血小板が急速に減少します。
同時にPT・APTT延長、フィブリノゲン低下、FDP上昇を伴います。
TTP(血栓性血小板減少性紫斑病)は溶血性貧血+神経症状+腎障害を伴い、ADAMTS13活性低下で診断されます。
血小板減少の検査アルゴリズム
日本内科学会雑誌(2022年)およびUpToDate(2024年改訂)による代表的な診断手順:
-
再採血(抗凝固剤変更):偽性低下を除外
-
他血球異常の有無:白血球・赤血球に異常があれば骨髄疾患を疑う
-
肝機能・脾腫評価(エコー)
-
感染症スクリーニング(B型・C型肝炎、HIV、EBウイルスなど)
-
自己抗体検査・骨髄検査(必要に応じて)
受診・再検査の目安
| 血小板値(/μL) | 対応方針 | 根拠 |
|---|---|---|
| 13〜35万 | 正常範囲 | ― |
| 10〜13万 | 軽度低下。3か月後再検査で経過観察可 | 多くは一過性変動 |
| 5〜10万 | 要精査。内科または血液内科受診 | 日本血液学会推奨 |
| 5万未満 | 出血リスク上昇。早期精密検査 | 同上 |
| 3万未満 | 出血傾向あり・治療適応 | ITP治療ガイドライン2023 |
まとめ
血小板の低下は、単なる採血誤差から骨髄疾患まで幅広い原因で起こるため、
まずは再検査で「本当に低いのか」を確認することが第一歩です。
持続的な低下や出血傾向がある場合は、**血液内科での精密評価(骨髄検査・抗体検査など)**を受けるようにしましょう。
参考文献(エビデンス)
-
日本血液学会編『造血器疾患診療ガイドライン 2023年版』
-
日本血液学会『免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)診療ガイドライン 2023』
-
日本内科学会雑誌 Vol.111 No.1(2022)「血小板減少の診断アプローチ」
-
George JN, et al. Thrombocytopenia: A clinical review. N Engl J Med. 2022;386:1819–1833.
-
Cines DB, et al. Immune thrombocytopenia. N Engl J Med. 2023;388:1732–1745.
-
UpToDate: Evaluation of thrombocytopenia in adults. (Accessed Oct 2025)
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
健康診断で「血小板が低い」と言われたら (2025年10月17日) インフルエンザワクチン予約受付を開始しました(2025年度) (2025年9月23日) 福岡県で「7,000円・即日発行」の法定健診 〜博多駅直結、働く人の時間を守るために〜 (2025年9月19日) 成人がインフルエンザワクチンを2回打ったらいけないの? (2025年9月18日) 院長が去年の余りインフルワクチンを打ってみた ― どれくらい意味があるの? (2025年9月12日)
血液検査の結果に「血小板が少ない」と書かれていると、不安になる方も多いと思います。
しかし血小板減少(thrombocytopenia)は… ▼続きを読む
ひろつ内科クリニックでは、2025年度のインフルエンザワクチン接種の予約受付を開始しました。
実際の接種開始は9月25日からとなります。
… ▼続きを読む
福岡県内の相場は8,000〜9,900円。それでも即日は少ない
福岡県内で行われている雇入時健診・法定健診は、多くのクリニックで8,000… ▼続きを読む
秋から冬にかけて、インフルエンザワクチンの接種シーズンが始まります。
患者さんからよく聞かれるのが「大人も子どもみたいに2回打った方がいい… ▼続きを読む
福岡でもインフルエンザの流行が始まっています。
当院にもそろそろ今年(2025/26シーズン)のワクチンが届く予定ですが、現時点ではまだ入… ▼続きを読む