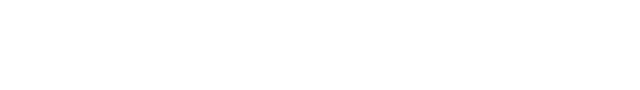銀杏中毒について総説
秋から冬にかけて旬を迎える銀杏は、茶碗蒸しや炒り銀杏などで親しまれています。しかし食べ過ぎにより「銀杏中毒」を起こすことが知られています。これは古くから日本で繰り返し報告されてきた食中毒であり、特に小児では重症化する可能性があるため注意が必要です。
銀杏中毒の原因成分
銀杏の種子には「4'-メトキシピリドキシン(MPN, ginkgotoxin)」が含まれています。
-
MPNはビタミンB6(ピリドキシン)の拮抗物質で、GABA合成酵素(グルタミン酸デカルボキシラーゼ)を阻害します。
-
その結果、抑制性神経伝達物質であるGABAが減少し、中枢神経系の過興奮から痙攣を引き起こします。
発生頻度と年次推移
-
厚生労働省の自然毒統計では、毎年数件~十数件の食中毒事例が報告されています。
-
多くは家庭内での摂取に関連し、飲食店での事例は稀です。
-
特に秋の行楽シーズン(10〜12月)に集中しています。
症例報告の特徴
-
小児例では7粒前後の摂取で痙攣を起こした症例が多数報告されています。
-
例:3歳児が7粒摂取後に嘔吐・痙攣を呈し、ピリドキシン投与で回復した報告(Hasegawa M, 1986)。
-
-
成人例では40粒程度の大量摂取が契機となることが多いですが、飲酒と併発して中毒を起こすことも知られています。
-
経過は一過性で、適切に対応すれば予後は良好です。
主な症状
-
消化器症状:嘔吐、下痢、腹痛
-
神経症状:めまい、頭痛、意識障害、けいれん
-
発症までの時間:摂取後1~12時間以内
-
重症例:痙攣重積に至り集中治療を要した例も報告あり
診断のポイント
-
「銀杏を食べた既往」が最重要。
-
症状が消化器+痙攣を伴う場合、特に小児では銀杏中毒を疑う。
-
血液検査で特異的マーカーはなく、臨床診断が中心。
鑑別疾患
-
てんかん発作
-
熱性けいれん
-
他の自然毒中毒(トリカブト、きのこ類など)
-
感染性胃腸炎
治療
-
対症療法が基本。
-
痙攣にはジアゼパムなどのベンゾジアゼピン系薬剤。
-
重症例ではピリドキシン(ビタミンB6)静注が有効とされており、多数の症例報告で痙攣改善が確認されています。
-
胃洗浄や活性炭投与は発症初期に検討されることがあります。
摂取許容量の目安
-
小児:7粒前後で発症例あり
-
成人:40粒前後で発症例あり
(ただし個人差が大きいため、安全量は「存在しない」とされています)
予防のために
-
子どもには銀杏を食べさせない、もしくは極めて少量にとどめる。
-
大人も食べ過ぎは避ける。
-
保存状態により毒性が変化する可能性があるため、古い銀杏の摂取は控える。
-
調理済みでも中毒リスクは残るため「炒れば安全」という誤解を避ける。
参考文献(エビデンス)
-
厚生労働省:自然毒のリスクプロファイル「ギンナン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188370.html -
日本中毒学会:自然毒中毒ガイドライン
-
Hasegawa M, et al. Ginkgo seed poisoning. Pediatrics. 1986;77(5):782-785.
-
Okamoto K, et al. Convulsions due to ingestion of ginkgo seeds. Pediatrics International. 2006;48(6):616-618.
-
宮田昌彦ほか:ギンナン中毒の臨床的検討. 小児科臨床. 1997;50(5):1031-1036.
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
ミドドリンによる高血圧の副作用 ― 起立性調節障害で処方される前に知っておきたいこと (2025年10月8日) 即効性のある漢方・じっくり効く漢方 ― 効果発現のスピードの違いを理解する (2025年10月6日) 銀杏中毒について総説 (2025年10月4日) 若者に多い「起立性調節障害」 ― 大人になっても続くことがある病気 (2025年10月2日) トランプ発言「アセトアミノフェンと自閉症」—エビデンスでどう読む? (2025年9月26日)
ミドドリンとは
ミドドリン塩酸塩(商品名:メトリジン)は、交感神経を刺激して血管を収縮させることで血圧を上げる薬です。
もともと 神経因… ▼続きを読む
「漢方は長く飲まないと効かない」と思っていませんか?
実は、**数時間で効果を実感できる“即効型の漢方”**もあれば、**数週間〜数か月か… ▼続きを読む
秋から冬にかけて旬を迎える銀杏は、茶碗蒸しや炒り銀杏などで親しまれています。しかし食べ過ぎにより「銀杏中毒」を起こすことが知られています。こ… ▼続きを読む
起立性調節障害とは
起立や体位の変化により、自律神経がうまく働かずに血圧や脈拍の調整ができなくなり、立ちくらみ・動悸・失神・強いだるさなど… ▼続きを読む
何が起きたのか(2025年9月の動き)
米国で、トランプ大統領が「妊娠中のアセトアミノフェン(一般名:アセトアミノフェン、米国ブランド:T… ▼続きを読む