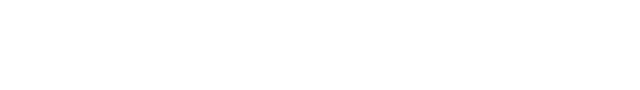潜伏梅毒(無症状梅毒)とは:定義・診断・治療
梅毒はトレポネーマ・パリダムによる性感染症です。典型的には皮疹やしこりで気づかれることが多いですが、症状が全くないまま血液検査で診断されることもあります。この状態は 潜伏梅毒(latent syphilis) と呼ばれます。
潜伏梅毒の定義
-
梅毒血清反応(RPR、TPHAなど)が陽性
-
臨床的な症状を認めない
分類は以下のとおりです。
-
早期潜伏梅毒(感染から1年以内)
再び第2期の症状が出ることがあり、感染性を有します。 -
後期潜伏梅毒(感染から1年以上)
性感染での伝播はほぼありませんが、妊婦では胎児に感染して先天梅毒を起こす可能性があります。
潜伏梅毒の診断
症状がないため、以下の場面で偶然に発見されることが多いです。
-
健康診断や妊婦健診
-
手術や入院前のスクリーニング
-
献血検査
潜伏梅毒のリスク
-
本人への影響:未治療で放置すると、大動脈瘤や神経梅毒など晩期合併症に進行する可能性があります。
-
周囲への感染:早期潜伏ではパートナーへの感染があり得ます。
-
母子感染:妊婦が感染している場合は先天梅毒の原因となります。
日本における治療(ガイドライン準拠)
日本性感染症学会・日本泌尿器科学会のガイドラインに基づきます。
-
アモキシシリン(AMPC)内服
成人:1日1.5〜3.0gを分割投与
- 早期梅毒(潜伏を含む):2週間
- 後期潜伏または不明期:4週間 -
プロベネシド
血中濃度維持の目的で併用する場合があります。 -
ペニシリンアレルギー例
ドキシサイクリン(100mg 1日2回、早期2週間/後期4週間)が代替療法として記載されています。 -
妊婦
アモキシシリンまたはペニシリンが推奨され、アレルギー例では脱感作の上でペニシリン投与を検討します。
日本での流行状況
厚生労働省の発生動向調査によると、梅毒の報告数は近年増加し、2023年には過去最多を記録しました。
東京都の病型別データでは「無症状病原体保有者(潜伏梅毒)」は毎年20〜40%程度を占めていますが、特別に増加しているわけではありません。
補足情報(海外ガイドライン)
-
CDC(米国):第一選択はベンザチンペニシリン筋注(BPG)。早期潜伏は1回投与、後期潜伏は週1回×3回投与。
-
WHO:同様にBPG筋注を第一選択としています。
まとめ
-
潜伏梅毒は「症状がなく、血清反応で診断される梅毒」。
-
日本ではアモキシシリン内服が第一選択肢として明記され、早期は2週間、後期は4週間投与。
-
ペニシリンアレルギー例にはドキシサイクリン、妊婦はアモキシシリンまたはペニシリン。
-
日本では全体の報告数が増加しているが、無症状例のみの増加は確認されていない。
参考文献
-
日本性感染症学会「性感染症診断・治療ガイドライン2020」
-
日本泌尿器科学会「性感染症診療ガイドライン2020」
-
厚生労働省 感染症発生動向調査(梅毒)
-
国立感染症研究所 梅毒関連解説
-
東京都感染症情報センター「梅毒の流行状況」
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
日本で使われるインフルエンザワクチンを網羅解説(2025/26シーズン) (2025年10月9日) インフルエンザワクチンの副反応発生確率を徹底解説 (2025年版・エビデンスレベル最高) (2025年10月5日) 潜伏梅毒(無症状梅毒)とは:定義・診断・治療 (2025年10月4日) サルモネラ食中毒とは?症状・原因・予防策を徹底解説 (2025年10月3日) 刺身や生魚で起こる細菌性腸炎 ― 主な原因菌と症状・予防策を徹底解説 (2025年10月3日)
日本の季節性インフルエンザワクチンは、大きく「不活化HAワクチン(注射)」と「経鼻弱毒生ワクチン(フルミスト)」、そして高齢者向けの「高用量… ▼続きを読む
毎年秋冬になると、多くの方がインフルエンザワクチンを接種します。
しかし、「副反応が怖い」「発熱したらどうしよう」と不安に感じる方も少なく… ▼続きを読む
梅毒はトレポネーマ・パリダムによる性感染症です。典型的には皮疹やしこりで気づかれることが多いですが、症状が全くないまま血液検査で診断されるこ… ▼続きを読む
サルモネラとはどんな菌か
サルモネラ(Salmonella属)は腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌で、世界中に広く分布しています。ヒトだけで… ▼続きを読む
日本の食文化に欠かせない「刺身」や「寿司」。世界的にも人気ですが、生魚を食べる文化は実は少数派です。その背景には「鮮度・保存・衛生管理」が厳… ▼続きを読む