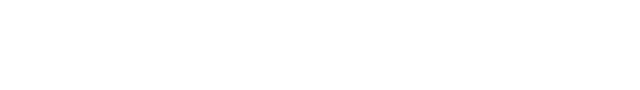梅雨入り前後に気をつけたい病気と対策
梅雨入りが近づくこの季節、気温と湿度の上昇により、体調を崩す方が増え始めます。実際、梅雨の前後は感染症・アレルギー・自律神経系のトラブルが多く報告されており、放置すると長引くこともあります。今回は、梅雨時期に増加する代表的な疾患と、科学的に裏付けられた対処法をまとめました。
① 気温差や湿度による「気象病(天気痛)」
-
症状:頭痛、めまい、関節痛、気分の落ち込みなど
-
原因:気圧や気温の変化により、自律神経が乱れることが主因です。
-
エビデンス:
-
自律神経と気圧変化の関連性は複数のレビュー論文(Yamamoto et al., Int J Biometeorol, 2020)で示されており、特に片頭痛や緊張型頭痛の誘因として知られています。
-
-
対策:
-
起床後に日光を浴びる、適度な運動、就寝リズムの安定など、自律神経の調整が重要。
-
酸素飽和度が安定しない方や低気圧に弱い方には、*酔い止め(抗ヒスタミン)や漢方(苓桂朮甘湯など)*の使用が有効なケースもあります。
-
② 食中毒・感染性胃腸炎の増加
-
症状:嘔吐、下痢、腹痛、発熱など
-
原因:高温多湿の環境で、細菌(Campylobacter, Salmonellaなど)やウイルス(ノロウイルス)が増殖しやすくなります。
-
エビデンス:
-
厚労省の疫学統計や、国立感染症研究所の年次報告では、6月から7月にかけて細菌性食中毒の件数が増加する傾向。
-
-
対策:
-
食材の保存温度・加熱の徹底、調理器具の消毒。
-
家族内感染防止には次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)による手指・トイレ・ドアノブ消毒が推奨。
-
③ 湿疹・汗疹・カンジダ性皮膚炎
-
症状:脇や股、皮膚の折れ目にできる赤み・かゆみ・ただれ
-
原因:汗と湿度で皮膚バリアが崩れ、細菌や真菌が繁殖
-
エビデンス:
-
Candida albicans による皮膚炎は、梅雨時の高湿環境下で発症リスクが約2倍になるとの報告あり(J Am Acad Dermatol, 2018)。
-
-
対策:
-
こまめな汗の除去、通気性の良い衣服の着用。
-
皮膚科的には、抗真菌外用剤(ラミシールなど)やステロイドとの併用が有効。
-
④ 咳・喘息の悪化(カビ・ダニによるアレルゲン暴露)
-
症状:長引く咳、喘鳴、夜間の息苦しさ
-
原因:湿気で室内の**カビ(Aspergillus spp.)やダニ(Dermatophagoides)**が増殖。
-
エビデンス:
-
室内カビ濃度と喘息発作の発生率には正の相関があり(Institute of Medicine, 2004)、アレルゲン曝露量が増えることで呼吸器症状が誘発されます。
-
-
対策:
-
換気の徹底・除湿機の使用・エアコンフィルターの清掃
-
気管支喘息のある方は吸入薬(ICS/LABA)や抗アレルギー薬の予防内服を事前に調整
-
受診の目安
-
気象の変化とともに頭痛やめまいが強くなってきた
-
咳が1週間以上続く、夜間に悪化する
-
嘔吐・下痢で水分がとれない、発熱がある
-
湿疹や皮膚のかゆみが広がってきた
こうした症状がある場合は、我慢せずお早めにご相談ください。季節の変わり目を元気に乗り切るためにも、予防と早期対応が重要です。
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから