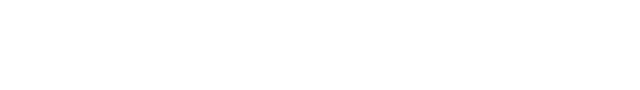膀胱炎を防ぐには?エビデンスに基づいた予防法まとめ
「トイレのたびに痛い」「何度も繰り返す」――そんな膀胱炎は、生活の工夫でかなり防ぐことができます。
今回は、医学的に効果が確かめられている予防法を中心に紹介します。
1. 水をしっかり飲む
最もシンプルで効果があるのがこまめな水分摂取です。
尿をためすぎると細菌が繁殖しやすくなります。
1日に1.5〜2Lの尿が出るくらいを目安に、水やお茶を少しずつ飲むのがおすすめです。
(腎臓や心臓に持病がある方は主治医にご相談ください)
2. トイレを我慢しない
「忙しいから」「外出先だから」と我慢するのは禁物です。
尿が膀胱に長くとどまると、細菌が増えやすくなります。
2〜3時間に1回はトイレに行くように意識しましょう。
3. 清潔の保ち方にもコツ
-
トイレットペーパーは前から後ろへ拭く
-
性交後はできるだけ早めに排尿する
-
石けんでの洗いすぎは避け、ぬるま湯でやさしく洗う
-
通気性のよい下着を選ぶ
これらは、尿道まわりの菌の繁殖を防ぐうえで大切です。
4. クランベリー製品
クランベリーに含まれる成分(プロアントシアニジン)が、細菌が尿路にくっつくのを防ぐ作用があります。
最新の研究でも、膀胱炎を繰り返す女性で再発を減らすことが示されています。
ジュースよりも無糖のカプセルやサプリのほうが実用的です。
ただし、すでに感染しているときの治療薬にはなりません。
5. D-マンノースは効果なし?
一時期注目されたD-マンノース(糖の一種)ですが、2024年の大規模研究で「効果なし」と結論づけられています。
現在は予防目的での使用は推奨されていません。
6. 閉経後の方は「膣の乾燥対策」も重要
閉経後はエストロゲンの減少で尿道や膣の粘膜が弱くなり、細菌が入りやすくなります。
婦人科で使う膣局所エストロゲン製剤には、膀胱炎の再発を減らす効果が科学的に確認されています。
内服ではなく「局所塗布」タイプです。
7. 体調・便通のケアも大切
-
便秘は腸内での細菌増殖を助けてしまう
-
冷え・ストレスも排尿リズムを乱しやすい
できるだけ規則正しい生活と十分な睡眠を意識しましょう。
8. 抗菌薬は「必要なときだけ」
抗菌薬の予防内服は一部で効果がありますが、耐性菌や副作用の問題があるため、医師の指導なしで続けるのは危険です。
症状が出たときは早めに受診しましょう。
こんなときはすぐ受診を
-
発熱(38℃以上)
-
腰や背中の痛み
-
嘔吐や寒気
-
妊娠中、または男性
これらは「腎盂腎炎」など上位の感染症のサインかもしれません。
放置せず、医療機関で検査・治療を受けてください。
まとめ
-
水をしっかり飲む(尿量1.5〜2L目安)
-
トイレを我慢しない
-
清潔な拭き方と通気性の良い下着
-
クランベリー製品の活用
-
閉経後は膣エストロゲンも選択肢に
これらを意識するだけで、膀胱炎の再発リスクを下げることができます。
参考文献(エビデンス)
-
Cochrane Database Syst Rev. 2023; “Cranberries for preventing urinary tract infections.”
-
JAMA Intern Med. 2024; Hayward G. et al. “D-mannose for preventing recurrent urinary tract infections.”
-
日本感染症学会/日本化学療法学会 尿路感染症ガイドライン(2023年版)
-
AUA Recurrent UTI Guideline 2023; EAU Urological Infections 2024 update
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
偽痛風とは?本当の痛風とどう違うのか (2025年11月3日) 膀胱炎を防ぐには?エビデンスに基づいた予防法まとめ (2025年11月2日) 中性脂肪高値で何が起こる?(何が危ない?何を防ぐ?) (2025年11月1日) 声がかすれにくい吸入薬はどれ? 〜嗄声(させい)を防ぐための正しい選び方〜 (2025年10月30日) 低血圧とは?原因・症状・治療方針を医学的に正確にまとめました【総説】 (2025年10月29日)
関節が急に腫れて痛む病気といえば「痛風」が有名ですが、実は似た症状を起こす「偽痛風(ぎつうふう)」という病気があります。
正式には「ピロリ… ▼続きを読む
「トイレのたびに痛い」「何度も繰り返す」――そんな膀胱炎は、生活の工夫でかなり防ぐことができます。
今回は、医学的に効果が確かめられている… ▼続きを読む
結論から。高トリグリセライド(TG)血症で臨床的に重要なのは大きく3つです。
1)動脈硬化(残余リスク)の増大、2)急性膵炎リスク、3)脂… ▼続きを読む
吸入薬で喘息を治療していると、「声がかすれる」「のどがヒリヒリする」と感じる人がいます。
これは**ステロイド成分(ICS:吸入ステロイド… ▼続きを読む
1. 低血圧とは
低血圧とは、収縮期血圧100 mmHg未満を指すことが多いですが、医学的には「症状を伴う低血圧」が臨床的意義を持ちます。… ▼続きを読む