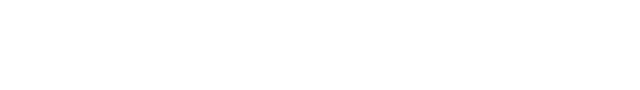ライム病とは?症状・診断・治療の最新知見まとめ
夏になると増える「マダニ媒介感染症」の中でも、世界的に有名なのがライム病です。日本ではあまりなじみがないかもしれませんが、実は注意が必要な疾患の一つです。本記事では、ライム病の原因から症状、診断、治療法、予防策まで最新のエビデンスに基づいて解説します。
ライム病とは?
ライム病(Lyme disease)は、スピロヘータの一種であるBorrelia属細菌(主にBorrelia burgdorferi)による感染症で、マダニ(Ixodes属)を媒介としてヒトに感染します。
名称は、1975年にアメリカ・コネチカット州の「ライム(Lyme)」で多発した関節炎患者から発見されたことに由来します。
日本での発生状況
日本でも北海道や長野などの一部地域で、ライム病を媒介するマダニ(シュルツェマダニなど)が確認されており、国内症例も年に数件報告されています。
厚労省の「人獣共通感染症」に指定されており、全数把握の感染症ではないため、実際の感染者数は過小評価されている可能性もあります。
主な症状
感染後の経過により、ライム病は以下の3期に分類されます:
第1期(数日~数週間以内)
-
遊走性紅斑(erythema migrans):感染部位から中心が薄くなる特徴的な赤斑(最大30cm)が出現(60–80%)
-
発熱・倦怠感・筋肉痛・関節痛・頭痛などの非特異的症状
第2期(数週~数か月)
-
顔面神経麻痺(ベル麻痺)
-
髄膜炎
-
心ブロックなどの心合併症(心筋炎)
第3期(数か月~数年後)
-
慢性関節炎(特に膝)
-
慢性神経障害(末梢神経炎、脊髄炎など)
診断方法
臨床診断
-
遊走性紅斑の出現があれば、疫学的背景(ダニ刺咬歴や流行地域への渡航)と合わせて臨床診断で治療開始可能です。
血清学的検査(2段階検査)
-
1次スクリーニング:ELISAやIFA法
-
2次確定検査:Western blot法
※感染初期(第1期)では感度が低いため、偽陰性に注意
治療法
抗菌薬治療(エビデンスグレード:A)
-
ドキシサイクリン(100mg 1日2回、10–21日間)
-
小児や妊婦にはアモキシシリンまたはセフトリアキソンが選択される
治療後症候群(Post-treatment Lyme Disease Syndrome, PTLDS)
-
治療後も数ヶ月〜年単位で疲労・筋肉痛・認知障害が残ることがあり、抗菌薬の再投与は推奨されていません(NIHおよびIDSAのガイドラインによる)
予防と対策
-
森林や草地での活動時は長袖・長ズボンを着用
-
ダニ除けスプレー(DEET等)の使用
-
帰宅後すぐに全身の皮膚チェック
-
早期にマダニを除去すれば感染リスクは大幅に低減
日本での注意点と医師の立場から
日本国内では「つつが虫病」「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」といった他のマダニ媒介疾患もあり、鑑別が必要です。顔面神経麻痺や関節痛を伴う不明熱患者では、海外渡航歴の有無にかかわらずライム病を念頭に置く必要があります。
参考文献・エビデンス
-
Steere AC, et al. "Lyme borreliosis." Nat Rev Dis Primers. 2016.
-
Stanek G, et al. "Lyme borreliosis: clinical case definitions for diagnosis and management in Europe." Clin Microbiol Infect. 2011.
-
日本感染症学会. ライム病診療ガイドライン.
-
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/lyme
-
厚生労働省 感染症情報:https://www.mhlw.go.jp
まとめ
ライム病は「マダニによる感染症の一つ」として過小評価されがちですが、適切な診断と治療が遅れると慢性化や神経障害を残す可能性があります。自然とのふれあいが増える季節だからこそ、マダニ対策と早期発見・早期治療が重要です。
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874