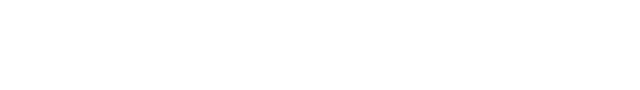自己幹細胞投与で死亡例――何が起きたのか?エクソソームとの“決定的な違い”も解説
はじめに
自由診療の再生医療で、自己脂肪由来幹細胞(ADMSC)の点滴投与を受けた患者が投与中に急変し、心停止で死亡した事案が公表され、厚生労働省は当該クリニックに緊急の業務停止命令を出しました(2025年8月29日)。まず、公開情報ベースで事実を整理します。
1) 事実関係(公表ベース)
-
厚労省は「再生医療等安全性確保法」に基づく疾病等報告を受理。慢性疼痛に対する自己脂肪由来間葉系幹細胞の点滴投与中に急変し、心停止→死亡が確認されたと公表。
-
使用した細胞は細胞加工施設で製造されたもの。現在も詳細原因は調査中。
-
これを受け、再生医療の提供停止命令が発出された。
2) なぜ幹細胞“投与”はリスクが高いのか
生きた細胞そのものを血管内に投与するため、以下のリスクが想定されます。
-
塞栓・循環動態の急変:細胞塊や投与速度によって微小血管が詰まり、肺循環や全身循環に急激な影響を与える可能性。
-
免疫・炎症反応:加工過程での不純物やサイトカインが強い反応を引き起こしうる。
-
腫瘍化・誤分化の懸念:中長期的に腫瘍原性が生じる可能性があり、研究段階では注意が必要。
-
製造・品質管理の難易度:ロット差、無菌性、エンドトキシン混入など厳格な管理が必須。
3) 日本の制度面:幹細胞とエクソソーム
-
幹細胞等の投与は「再生医療等安全性確保法」の対象。必ず提供計画の届出、倫理審査委員会の承認、細胞加工施設での製造が必要。今回の死亡例も同法に基づき報告された。
-
エクソソーム投与は現状では未承認で、有効性・安全性のエビデンスは確立していません。日本再生医療学会や京都大学CiRAからも「現状は研究段階であり、規制の枠組み整備が必要」とのステートメントが出ています。
4) 幹細胞投与とエクソソーム投与の“根本的な違い”
| 観点 | 幹細胞投与 | エクソソーム投与 |
|---|---|---|
| 本体 | 生きた細胞 | 細胞外小胞(ナノサイズのベシクル) |
| 主な理論作用 | 組織再生、免疫調整 | miRNAやタンパク質のシグナル伝達 |
| 急性期リスク | 塞栓・免疫反応・感染リスク | 物理的塞栓は低いが、不純物・規格不一致のリスク |
| 規制 | 再生医療等安全性確保法の枠組み | 監督の枠組みが未整備、指針の議論中 |
| エビデンス | 一部承認疾患はあるが多くは未確立 | 臨床有効性は未確立、研究段階 |
5) 受療を検討する際のチェックポイント
-
それは承認医療か?自由診療か?
-
提供計画の届出や審査委員会の承認はあるか?
-
投与経路と適応疾患は妥当か?
-
製造過程・品質規格が明確か?
-
有害事象の公開や救急体制は整っているか?
-
広告に「効く」「治る」といった断定的表現が使われていないか?
当院のスタンス
-
当院では幹細胞投与(細胞点滴)は行っていません。
-
エクソソーム点滴は疾病治療を目的とするものではなく、未承認・有効性未確立の自由診療であることを必ず説明しています。
-
効果を保証するものではなく、安全管理と情報提供を最優先にしています。
→ 自由診療の詳細は 自由診療価格表 をご覧ください。
まとめ
-
2025年8月に自己幹細胞投与による死亡例が報告され、厚労省は緊急の提供停止命令を出しました。
-
幹細胞投与は生きた細胞を体内に入れるための固有リスク(塞栓、免疫反応、品質管理)があり、エクソソーム投与とは本質的に異なります。
-
どちらも現時点で確立した承認医療ではなく、研究段階であることを理解したうえで慎重に判断する必要があります。
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
参考文献
-
厚生労働省 報道発表「再生医療等の提供における疾病等報告について」(2025年8月)
-
日本再生医療学会「エクソソームに関する見解」2023年
-
Kyoto University CiRA「幹細胞外小胞研究に関するステートメント」2024年
-
Uemura N, et al. N Engl J Med. 2001;345:784-789.
-
Fukase K, et al. Lancet. 2008;372:392-397.