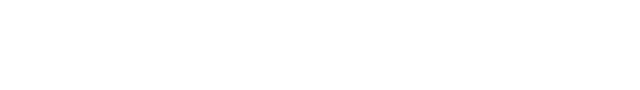咳が止まらないのは、神経のせいかも?“咳感受性亢進症候群”という考え方
最近、「風邪が治ったのに咳だけが何週間も止まらない」という相談がとても増えています。
レントゲンは異常なし、熱もなく、聴診でも特に問題が見つからない。
でも、咳だけがずっと残る――
こうしたケースで注目されているのが、咳感受性亢進症候群(Cough Hypersensitivity Syndrome, CHS)という概念です。
咳感受性亢進症候群って何?
簡単に言うと、
「咳の神経が過敏になってしまい、ちょっとした刺激でも咳が出てしまう状態」
のこと。
この考え方は2014年に提唱され、2021年の日本呼吸器学会「慢性咳嗽診療ガイドライン」にも正式に取り入れられています。
それまで「原因不明の咳」とされていたものに、一つの説明を与えてくれる概念です。
なぜ神経が敏感になるのか?
CHSのきっかけとしてよくあるのは:
-
風邪やコロナ後に咳だけが残る
-
GERD(胃食道逆流症)による微細な刺激
-
アレルギー性炎症の影響
-
ストレスや不安による神経系の変調
などがあります。
特に2020年代以降は、感染症の流行後に咳が長引く人が非常に多くなっており、CHSの重要性が見直されています。
どうやって診断するの?
CHSに特別な検査法はありません。
呼吸器専門の医療機関では、呼気NO測定やスパイロメトリー、気道過敏性試験などを通して、より精密な診断が行われます。
当院のような地域の内科クリニックでは、
-
胸部X線
-
問診(咳の性質や誘因、時間帯など)
-
他疾患(咳喘息、GERD、後鼻漏など)の除外
-
治療的診断(薬への反応)
などを組み合わせて、まずは初期的なアセスメントを行います。
必要があれば、専門の呼吸器内科にご紹介することも可能です。
治療はどうするの?
CHSの本質は「神経の過敏さ」にあるため、従来の咳止めでは効果が薄いこともあります。
実際の治療は、咳を引き起こしている可能性のある背景を見ながら、以下のような薬を選択していきます。
一例として:
-
麦門冬湯、半夏厚朴湯などの漢方薬:喉や気道の過敏をやわらげる働き
-
ゲフォピキサント(商品名:リフヌア):
日本でも2023年に承認された、咳の反射を抑える神経系の新しい薬。
P2X3受容体に作用し、「のどのイガイガ感」からの咳を軽減するとされています。 -
必要に応じて、抗ヒスタミン薬やアレルギー治療薬、GERD治療薬(PPI)などを併用することもあります。
最後に:地域の内科でできること、そして限界も
慢性咳の診療は、本来は呼吸器内科の専門領域です。
ですが、日々の外来では、まず**「何か大きな異常がないか」「咳止めで済ませていい話ではないか」**を見極めることが求められています。
ひろつ内科クリニックでは、
「咳が長引いているけど、どこに相談したらよいかわからない」
という方の初期的な評価や、必要に応じた専門医紹介を行っています。
【参考文献・エビデンス】
-
日本呼吸器学会 慢性咳嗽診療ガイドライン(2021年改訂)
-
Morice AH et al. Cough Hypersensitivity Syndrome. Lancet Respir Med. 2014
-
厚生労働省 医薬品審査資料:ゲフォピキサント(リフヌア錠)2023年承認
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874