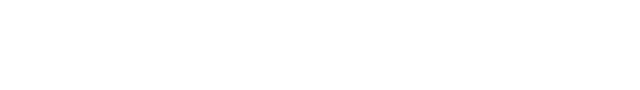夏に多い?膀胱炎の正体と正しい治療法
「水をたくさん飲めば治る」はウソ?
こんにちは、ひろつ内科クリニックの院長・廣津です。
夏になると「トイレが近い」「おしっこをすると痛い」「下腹部が重い」といった症状で来院される方が増えてきます。
この症状、多くの場合は急性膀胱炎が原因です。
一見すると軽症に見えるこの疾患ですが、放置すると腎盂腎炎に進行するリスクもあり、油断は禁物です。
今回は、夏に膀胱炎が多くなる理由や正しい対応について、エビデンスをもとに解説します。
■ 夏に膀胱炎が増える理由
膀胱炎の大半は、大腸菌などの腸内細菌が尿道から膀胱に侵入して炎症を起こすことで発症します。
なぜ夏に増えるかというと、以下のような要因が重なるためです。
-
脱水による尿量減少 → 尿が濃くなり、細菌が膀胱にとどまりやすくなる
-
発汗による膀胱内環境の変化 → トイレ回数が減り、排菌の機会が減少
-
冷房や水着などによる局所の冷え → 局所の免疫力が低下
-
性交渉の増加(特に若年女性) → 物理的な刺激で尿道炎・膀胱炎のリスク上昇
とくに女性は尿道が短く、膣や肛門と近接しているため、男性に比べて罹患率が圧倒的に高いのが特徴です。
■ 症状と受診すべき目安
以下の症状がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診してください。
-
排尿時痛(ツーンとした痛み)
-
頻尿(30分~1時間ごと)
-
残尿感
-
下腹部の違和感
-
血尿(特に肉眼的血尿)
また、以下の症状がある場合は腎盂腎炎の可能性があり、即時の抗菌薬投与が必要です:
-
発熱(38℃以上)
-
背部痛・腰痛
-
吐き気・嘔吐
-
全身の倦怠感
■ 検査と治療
当院では、必要に応じて以下の検査を当日中に実施・評価しています。
-
尿定性検査:亜硝酸塩・赤血球・白血球の有無を確認
-
尿培養(必要時):原因菌の特定と抗菌薬感受性の確認
-
血液検査(CRP、白血球数):腎盂腎炎の可能性を除外
-
腹部エコー(膀胱残尿測定):再発例や残尿感のある方で実施
■ 治療薬の選択(初発・単純性の場合)
日本の診療ガイドラインでは、ホスホマイシン(商品名:ホスミシン)単回投与が第一選択とされています。
ただ、実際の診療では「一度で治るのが不安」「続けて飲みたい」といった患者さまの希望も多く、
当院ではそうした心情も踏まえて、数日間の継続投与も柔軟に対応しています。
また、再発例や腎盂腎炎の合併が疑われる場合は、ST合剤(バクタ)やセフェム系、必要に応じて他剤を使用します。
患者さんの体質・病歴・年齢に応じて、個別に最適な治療を選んでいます。
■ 膀胱炎は「水で流せば治る」わけではない
「水分をたくさん摂れば自然に治る」と誤解されがちですが、これは予防には有効でも、治療には不十分です。
すでに発症している場合には適切な抗菌薬治療が必須です。
とくに再発を繰り返す方や、排尿痛が続く方は放置せず、しっかり治し切ることが重要です。
■ 再発を防ぐ生活習慣のポイント
-
水分をこまめにとる(1日1.5〜2Lが目安)
-
尿意を我慢しない
-
排尿後は前から後ろに拭く(女性)
-
性交後はできるだけ早く排尿する
-
下腹部・下半身の冷えを避ける(夏でも冷房に注意)
まとめ:軽く見ないで、きちんと治す膀胱炎
夏場の膀胱炎は珍しくありませんが、「たかが膀胱炎」と甘く見ると、腎盂腎炎など重症化のリスクもあります。
当院では、必要な検査をその日のうちに実施し、診断から治療まで完結できる体制を整えています。
症状に心当たりがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 自由診療メニュー・価格はこちら
ひろつ内科クリニック受診予約はこちらから
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08874
【参考文献・エビデンス】
-
日本化学療法学会編「尿路感染症診療ガイドライン2023」
-
厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き(2017)」
-
日本泌尿器学会「女性の膀胱炎診療に関するガイドライン」
-
Foxman B. “Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs.” Dis Mon. 2003